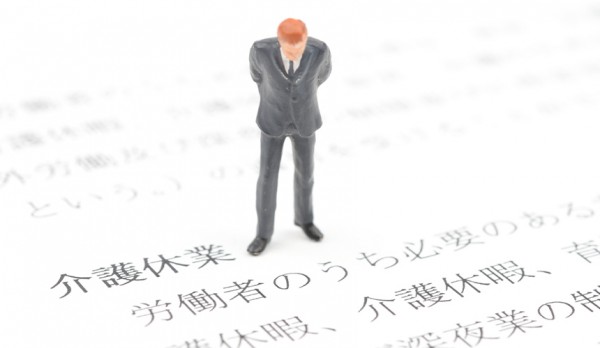介護休業法の改正で「仕事と介護の両立」は可能?
わかりやすく解説
2025年4月、介護休業に関する法律が改正されます。今回の改正では、「仕事と介護の両立支援の強化」が特徴です。しかし、「具体的に何が変わったの?」「どのようなメリットがあるのだろう?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、介護休業法の今回の改正内容について、わかりやすく解説します。
少子高齢化が進む近年では、誰もが「働きながら介護」に直面する可能性が高まっています。仕事と介護を両立させたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
そもそも「介護休業法」とは
介護休業法※1とは、「家族の介護を行う人が、介護のために仕事を休むことができる制度」を定めた法律です。
超高齢化社会を迎えた日本では、働きながら家族の介護をする人(ビジネスケアラー)が増加しています。しかし、仕事と介護の両立はとても難しく、介護のために仕事を辞めざるを得ない人がいるのが実情です。経済産業省では、労働者の介護による経済損失は2030年に約9.2兆円と試算しており、社会に大きな影響を与えることが予測されます。
介護休業法は、このような状況を改善するべく、仕事と介護の両立を支援し、介護離職を防ぐことを目的に制定されたものです。
※1:介護休業法の正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。この法律では、介護だけでなく、育児に関する支援なども規定されています。
2025年介護休業法の改正ポイント
今回の介護休業法の改正では、主に4つの点が大きく変更されました。
2025年介護休業法の改正ポイント
- 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
- 介護離職防止のための雇用環境整備
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
- 介護のためのテレワーク導入
それぞれ詳しく解説していきます。
①介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
介護休暇を取得できる労働者の要件のうち、「継続雇用期間6ヵ月未満の労働者は除外」という制限が撤廃されました。これにより、より多くの労働者が介護休暇を利用できるようになります。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
|
<介護休暇を取得できない労働者> ①週の所定労働日数が2日以下 |
<介護休暇を取得できない労働者> ①週の所定労働日数が2日以下 |
②介護離職防止のための雇用環境整備
事業主は介護離職を防止するために、以下の4つのいずれかを実施することが義務化されました。
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
- 自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
上記のいずれかが実施されると、労働者が「自分が受けられる介護支援」について、イメージしやすくなります。
③介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
介護離職を防ぐために、労働者への個別の周知や意向確認が義務付けられました。
「家族の介護をしなければならない」と労働者から申し出されたら、事業者はその労働者に対して、以下の事項について個別に周知し、支援制度を利用するかの意向を確認する必要があります。
| 周知事項 | ①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ③介護休業給付金に関すること |
|---|---|
| 周知・意向の確認方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか ※①はオンライン面談も可能、③と④は労働者が希望した場合のみ |
事業者は労働者に対して、取得や利用を控えさせるような周知や意向確認はできません。
さらに、事業者は労働者が介護に直面する前に、介護両立制度等の情報を提供することが義務付けられました。
介護に直面する前とは、具体的に以下のどちらかの期間を指します。
-
労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
- 労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間
④介護のためのテレワーク導入
仕事と介護を両立するために知っておきたい制度・措置
いざ介護が必要となったら、どのような制度や措置が使えるのでしょうか。
ここでは、仕事と介護を両立するために知っておきたい制度や措置について、今回の法改正も踏まえてまとめました。
ここで紹介する制度・措置は、いずれも法律で認められた権利です。仕事と介護の両立が難しいと感じたら、気兼ねなく申請しましょう。
①介護休業
介護休業とは、要介護状態の家族を介護するために、仕事を休むことができる制度です。
まとまった期間、仕事を休めるため、介護に専念できます。
| 対象となる労働者 | 要介護状態※にある対象家族の介護や世話を行う労働者 ※負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態 |
|---|---|
| 対象外となる労働者 |
|
| 対象となる家族 | 配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 |
| 取得可能な日数 | 対象家族1人につき93日まで ※3回まで分割取得も可能 |
| 給料 | 原則として支払われない ※事業者によって異なる |
| 介護休業給付 | 受給要件を満たす場合、支給される ※「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」より算出 (例)月額30万円程度の場合、支給額は20.1万円程度 |
| 手続き | 原則2週間前までに書面等で事業者に申請 |
②介護休暇
介護休暇とは、要介護状態にある家族を介護するために1時間単位で取得できる休暇です。
日常生活の介助や通院の付き添いなどで利用することができます。
| 対象となる労働者 | 要介護状態※にある対象家族の介護や世話を行う労働者 ※負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態 |
|---|---|
| 対象外となる労働者 |
|
| 対象となる家族 | 配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 |
| 取得可能な日数 | 年5日まで取得可能 ※2人以上の場合は年10日 |
| 給料 | 原則として支払われない ※事業者によって異なる |
| 介護休業給付 | なし |
| 手続き |
|
介護休暇と介護休業の違いについては、こちらの記事『介護休暇・介護休業、家族の介護のために会社を休むならどっち?』で詳しく解説していますので、併せて参考にしてください。
③所定外労働・時間外労働の制限
介護を行う労働者は、所定外労働や時間外労働(残業)を減らすことができます。
| 対象となる労働者 | 要介護状態※にある対象家族の介護や世話を行う労働者 ※負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態 |
|---|---|
| 対象外となる労働者 |
|
| 対象となる家族 | 配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 |
| 時間外労働の制限 |
|
| 取得可能な期間 | 1回の請求につき、1ヵ月以上1年以内 |
| 請求回数 | 制限なし |
| 手続き | 開始日の1ヵ月前までに、書面等により事業者に請求する |
ただし、例外として、事業の正常な運営を妨げる場合は、事業者は請求の拒否が可能です。
④深夜業の制限
介護を行う労働者は、申請手続きを行うことで、深夜業(午後10時から午前5時)の労働が免除されます。
| 対象となる労働者 | 要介護状態※にある対象家族の介護や世話を行う労働者 ※負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態 |
|---|---|
| 対象外となる労働者 |
|
| 対象となる家族 | 配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 |
| 取得可能な期間 | 1回の請求につき、1ヵ月以上6ヵ月以内 |
| 請求回数 | 制限なし |
| 手続き | 開始日の1ヵ月前までに、書面等により事業者に請求する |
ただし、例外として、事業の正常な運営を妨げる場合は、事業者は請求の拒否が可能です。
⑤所定労働時間短縮の措置
介護を行う労働者は、申請手続きを行うことで、所定労働時間を短縮するなど支援が受けられます。
事業者は、労働者からの申請があった場合、以下のいずれかの措置を講じなければいけません。
- 所定労働時間を短縮する制度
- フレックスタイム制度
- 始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げ
- 労働者が利用する介護サービスの費用助成その他これに準ずる制度
| 対象となる労働者 | 要介護状態※にある対象家族の介護や世話を行う労働者 ※負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態 |
|---|---|
| 対象外となる労働者 |
|
| 対象となる家族 | 配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 |
| 取得可能な期間/回数 | 対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年以上の期間内に2回以上 |
介護休業法改正が労働者にもたらすメリット
最後に、今回の改正によって労働者が得られるメリットについてご紹介します。
働き方の選択肢が増える
介護を行う労働者に対して、テレワークを選択できるようにする努力義務が追加されました。テレワークが導入されると、働き方の選択肢が増え、介護と仕事の両立がしやすくなります。
精神的な負担を減らせる
今回の改正では、介護が必要な状況になる前に介護に関する情報が得られ、いざというときに支援や相談が受けやすい体制が導入されました。これにより、介護をしながら働く人にとって、精神的な負担が大幅に軽減されることが期待できます。
支援制度・措置を活用して、介護と仕事の両立を目指そう
今回の介護休業法の改正により、介護を担う労働者の負担が減ることが期待されます。
介護と仕事が両立しやすい環境が整うと、介護離職という選択をせずにすむ人が増えるでしょう。
しかし、いくら法的に認められた権利とはいえ、一方的に行使するとトラブルが生じます。実際に制度を利用するには、事業者や周囲の人とのコミュニケーションを行い、適切な支援を受けることが大切です。